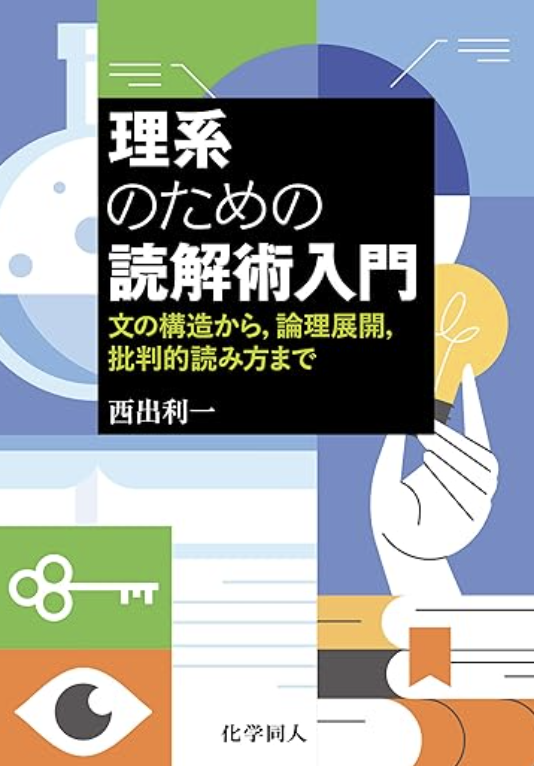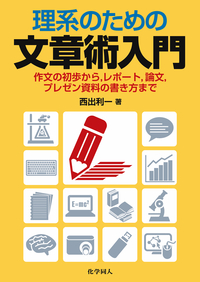目次
1.つなぐ言葉
日本語には,文と文あるいは文節と文節をつなぐ言葉が多くあります.
文と文は接続詞がつなぎます.
理系文(科学技術文)では,
「また」,「さらに」,「しかし」,「だが」,
「ところが」,「そして」,「だから」,
「したがって」,「つまり」,「ただし」
がよく使われます.
順接や逆接などさまざまに文をつなげます.
文をつなぐ別の言葉もあります.
たとえば,「一方」,「その結果」,「もちろん」,などです.
これをつなぎ語といいましょう.
文と文をこれらの言葉でつなぐと,意味が取れやすい文章をつくることができます.
文例1
CO2排出量の削減が強く要求されている.しかし,実効ある対策が乏しい.
大量に放出されたCO2により地球温暖化が進行している.その結果,大型台風や冬期の高温など異常気象が頻発するようになった.
このように接続詞やつなぎ語をうまく使うと,論理的で引き締まった文章が書けます.
文節と文節をつなぐには接続助詞を使います.
理系文でよく出てくる接続助詞は
「が」,「て」,「ので」,「から」,「たり」
などです.
文例2
陸地から海洋にプラスチックゴミが大量に流出しているので,現況調査が必要である.
デバイスAの応用分野を開拓したり,性能を改良するなど開発部門の成果は大きい.
これらの文も意味がよくわかり,論理的で締まりのある文です.
さらに,動詞や助動詞の連用形(たとえば,「~しており」,「~され」など)
も文節をつなぎます.
これの使い方については,
「論理的で締まりのある短文を書く方法 その2―動詞・助動詞の連用形を多く使わない」
を参照してください.
2.日本語文は長くなりやすい
接続助詞は便利な言葉です.
でも,これを多く使うと言葉が延々と続く長文になります.
私たちは文例3のような長文を書く傾向があります.
文例3
この文例は5個の接続助詞(下線部 が,から,ので)で文節が長々と続き,
文字数は171文字もあります.
さすがにこれは長すぎますし冗長です.
意味もよく理解できません.
理解しなければならない文節が途切れなく続くからです.
3.長文を短文化する
論理的で締まりのある短文で文章を書くと,
説得力のある文章ができあがります.
文の長さはせいぜい110文字程度まででしょう.
A4判用紙だと3行です.この長さを目安にするとよいです.
文例3を改訂してそのような文章につくり変えましょう.
具体的な方法は以下のとおりです.
② 改めて文を書き始めます.このとき,必要に応じて接続詞やつなぎ語を使います.
文例4に改訂例を示します.
文例4
3箇所の接続助詞を削除して文を終わらせました(二重下線部).
最初の箇所は,「と考えられている.これまで」と,
接続助詞を削除して文を終えて,改めて次の文を書きました.
2番目と3番目は,それぞれ接続詞「しかし」と「だから」を使いました.
2番目は逆接の「しかし」でつなげました.
前文と逆のことが書かれているからです.
3番目は理由・原因の「だから」を使いました.
前文が後文の理由・原因になっているからです.
こうすると,前文と後文が論理的につながります.
接続助詞は2個に減りました(下線部).
文章は4文に分かれ,それぞれ,55,46,26および48文字と短くなりました.
結果,論理的で締まりのよい文章に改訂できました.
このように,接続助詞を使いすぎないで,接続詞やつなぎ語をうまく使うと,
論理的で引き締まった短文からなる文章を書くことができます.
4.まとめ
1)日本語には接続詞や接続助詞など,文と文あるいは文節と文節をつなぐ言葉があります.
2)接続助詞は文節と文節をつなぐ便利な言葉です.しかし,それを多く使うと長々と続く冗長な長文を書いてしまいます.それは意味が取りにくくわかりにくい文です.
3)改訂法は以下のとおりです.
①接続助詞を削除して,文を終わらせます
②改めて文を書き始めますが,必要に応じて接続詞やつなぎ語を使います
こうすると,論理的で締まりのある短文からなる文章ができあがります.